目次
このブログは 現在57歳母である私と25歳次男である僕とで、これまでの子育て親育てに関して、親の立場で考えたことが子供の立場ではどうだったのか?親として伝えたかったことが伝わってたのか?などをやり取りしてます。
の後には母親である私の投稿。
の後には息子である僕の投稿です。
こんにちは。
今回はそろそろ準備の時期、進路についてです。
うちの息子達は小学校受験、中学受験、大学受験はしていません。
なので主に高校受験の話しを。
進路を決める過程で心掛けていた事についてお話ししたいと思います。
お仕事されてないお母さんお父さんには時間がたくさんありますし、お仕事されてるお母さんお父さんは、職場の人からいろんな地域や世代の情報が集められますよね。
子供よりも親の方が広い視野と情報源で収集できると思います。
初めはやはり学校のホームページ。
でも、ホームページだけではわからない事が多いし、正直いい事しか書いてないかな(^^;)
そんな時、パート先やママ友でその学校の近くにに住まれてる人や、その学校出身の人がいたりしたらラッキー、生の声が聞けます。
もちろん学校での進路説明会や進路指導の先生からも情報を得る機会がありますが、息子達の在籍中学からは、過去に1人も受験した事のない高校が志望校だったので、先生からは合格ラインなどよくわからないと言われました。
高校受験に関して言えば普通科の他に工業科、商業科、農業科、と今はもっと細分化されていて名前を聞いただけでは何を勉強するのかわからないような科もたくさんあります。
長男は小さい頃からものづくりが大好きだったので、早くから工業科に行く事を決めていました。
次男は最初、近くの普通科公立高校に行きたいと言ってました。
仲良しの友達がそこに行きたいって言ってるから、その学校に行けばちょっと頭良いって思われるから、などと単純な動機だったはずです。
中学生って志望校を選ぶ時、単に高校の事しか見えていないんです。
でも、一番重要なのは高校卒業後の進路。
進学する高校や科によって卒業後の進路にとても影響する事を具体的に話しました。
そして、興味はなくても他の科の学校のオープンスクールに行ってみる事を強く勧め3つの高校のオープンスクールに参加しました。
中学生の時、僕は特にやりたいことがありませんでした。
なのであまり深く考えることなく、近くの高校へ行き、とりあえず大学へと考えてました。
割と一般的というか、みなさんこんな感じじゃないでしょうか。
そんなみなさんに一言。
それじゃダメ!視野が狭いです。
偉そうに言ってますが、僕自身もめちゃくちゃ視野が狭かったんです。
その視野を広げてくれたのは言わずもがな母でした。
その母が情報収集に力を入れてくれたからこそ、選択範囲がすごく広がりました。
感謝してます。
いくら話しを聞いてもホームページを見てもやっぱり実際に行って見なければわからない事がたくさんあります。
まず、通学方法。
通学にかかる時間、電車やバスに乗らなければならない場合など、中学とは違った通学方法を体験してみる。
学校の雰囲気や制服、校則、部活。
オープンスクールの日に先生のお手伝いをしている在校生はきっと選りすぐりの優等生。
なので、それ以外の生徒の様子を最寄駅や近くのコンビニなどで観察。
長男は工業科を3校
次男は工業科2校普通科1校
のオープンスクールに参加しました。
オープンスクールの日程が重なったりで3校が限界だったけど、3校も行ってたのはうちの息子達ぐらい。
ほとんどの子供達は1つしか行ってないようでした。
第一回進路調査の時は近所の普通科に行きたいと言っていた次男、このオープンスクールであっさり工業科へ志望校を変えました。
普通科に見学行ったけど、おもろなかったわ。
実際に行きたいと思う高校の見学ができるオープンハイスクール。
友達も多くいるし、近くだからと普通科の高校を志望していましたが、母から、
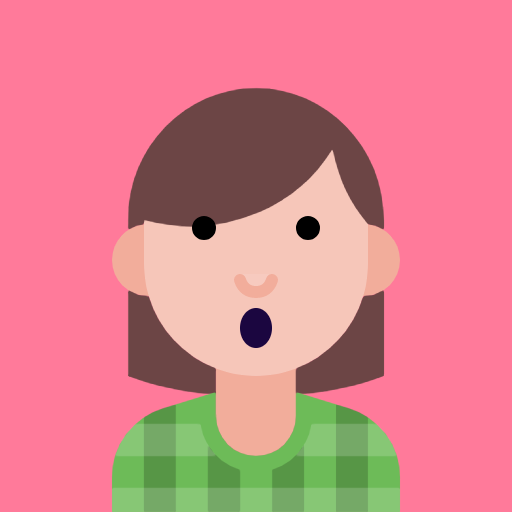
もし大学へ行くか就職するか決めていないのなら、工業科も行ってみたら?
と提案がありました。
工業科?
いやいや、そんな男子校的なところ、楽しくないやんか。
高校こそ青春、俺はバイトして稼いで遊ぶんや~。
と将来のことなんて考えていない安直な気持ちでした。
しかし、オープンハイに行き工業科がすごく楽しそうに感じました。
そして背中を押すように母から、
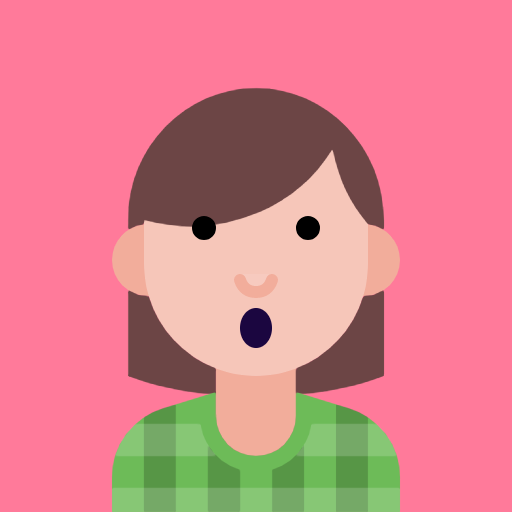
工業科やったら、就職にも強いし、大学行きたくなったら受けれるで。
なるほどねと。
選択肢が広がるじゃない、と。
なにせ普通科のオープンハイに行った時に、中学校の3年間をまた繰り返すような気がしてつまらないと思ったんです。
半ば無理やり工業科のオープンハイに行かされたのですが、行ってよかったです。
親にはこんな人になって欲しいとか、ここの学校に入って欲しいやこんなスポーツをして欲しいなどの想い、少しあったりしますよね。
でも、それを口に出してしまうと子供がそっちの方へ寄せてしまうんじゃないかと思うので、言わないようにしていました。
子供って普段全然言う事きかないけど、少なからず親に喜んで欲しいと思ってるところがあるようで、特に自分の強い希望が無い場合、親の希望する方へと寄せてしまうんじゃないかと。
息子達にはどんな事でも出来るだけ
ニュートラルな気持ちで決めて欲しかったんです
あの時お母さんがここに行ってと言ったからとか、お父さんがここが良いと言ったから、なんて言い訳をさせないためにも
選んだのは自分、決めたのも自分。
3年間の高校生活を終えた時、自分の決断がどういう結果をもたらしたのかが分かる、恐らく人生最初の機会、それが高校受験かなと思います。
僕の場合、大学へは行きなさいや、高校は偏差値の高いところへ、など言われたことがありません。
なので全て自分で決断しました。
もちろん、母の意見もいろいろ聞き、それを参考にしました。
自分で選ぶのが億劫だからと、親の意見をそのまま鵜呑みにすることもできたんですが、自分の人生、自分が決断しなきゃでしょう。
そう思わせてくれてのは母です。
正直、オープンハイにたくさん行くのは面倒くさかったし、一緒に行く友達もいないし、学力がどれだけいるかわからないから、一生懸命勉強しないといけないので大変でした。
でも、おかげさまで今は後悔してません。
・子供側は親の意見をそのまま鵜呑みにするのか、参考意見としてとるのか。
・親側は、子に対して教養と強要を間違えていないか。
子供自身の決断力が問われますが、大人になっていく中で大切なことです。
高校に入学すると早いうちから大学か専門学校への進学か就職か、理系か文系かなど大まかな進路は決めなければならなくなります。
理系文系に関しては選択する教科が変わるので決定後の変更は難しいのですが、進学か就職かは少しあとでも大丈夫だったんじゃないかな?
次男はラグビー 推薦で大学へ行くか就職をするか悩んでいる様子でした。
結局就職を選択しましたが、どうしても行きたい企業や具体的な職種はありませんでした。
3者面談、先生が勧めてくれた某上場企業、お母さんどうですか?と聞かれたけど、正直なところ働くのは次男だし、私の意見いる?ぐらいの気持ちでした(^^;)
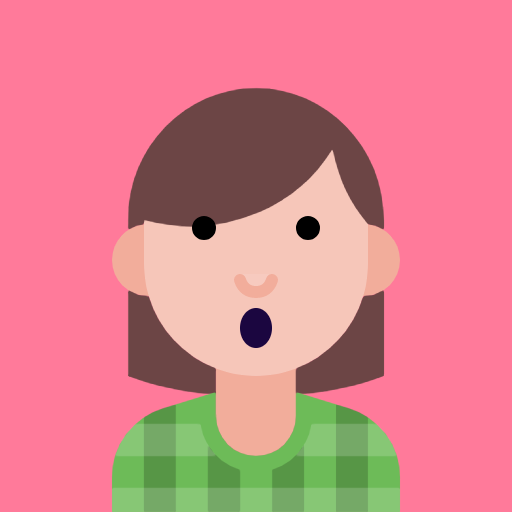
お任せします
と一言、あっさり3者面談は終わりました。
中学時代の友達はみな高校卒業後大学や専門学校に行きました。
今はそれぞれ就職し、仕事の愚痴など言い合っています。
そんな時に、僕が工業科に行って就職したという話をたまにするのですが、
- 高卒で就職ってのが視野に無かったなぁ
- 高卒でも大手の会社から求人来てるんや!
- 工業科やったら選択肢増えてたなぁ
と友人からよく言われます。
これが世の中の子供の声なんだなぁと思いました。
親がどう子供にアドバイスできるか、とても大切ですね。
これが正解というわけではありませんよ。
僕の周りがそう言ってるという事実、参考程度に…
友達が多い近くの普通科志望の僕が、工業科へ変更した理由を説明してきました。
オープンハイに行くことってとても面倒くさいのですが、とても大事なことだというのを理解していただけたでしょうか?
親は、広い視野で選択肢を広げ、より良い決断をできるよう子供に促してあげることで、子供は自分で決断する力を身につけます。
その決断力は大人になってからもからも大事なことじゃないですか??
先ほどから常々記載している通り、僕は高卒で就職し、現在は社会人生活7年と少しが経ちました。
そしてここ2年前くらいから、自分のしたいことを強く考えるようになり現在絶賛勉強中です。
この8年間、もちろん転職など考えることもありました。
ただ、高卒というのがすごくネックに感じました。
どの求人を見ても条件に大卒、院卒とほぼ記載されています。
なので高卒の僕には選択肢が無いなぁと思ってました。
だから大学へ行ったほうが良かったか?と言われると、正直五分五分。
今の勤めている会社は大卒で就職しようものならそれなりの大学じゃないと出来ないし、高卒にしては十分な年収。
勉強が好きでは無かったので、大学へ行っても遊んでたかなぁと。
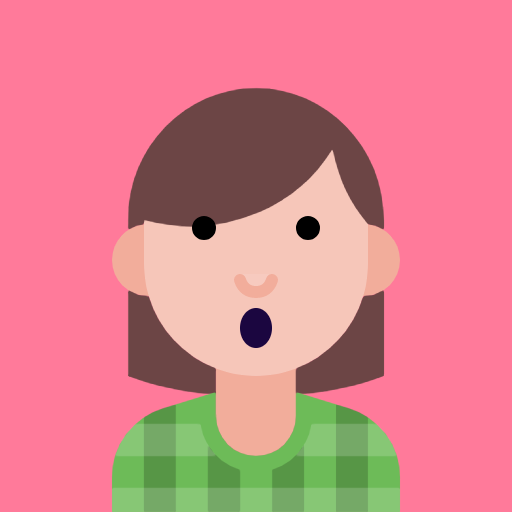
私もそう思う(^^;)
でも大卒という肩書きは今の日本社会において、書面上絶対条件かのような重さがあります。
なので今の僕からしても、どちらが正解か分かりません。
ただ補足として、大卒と記載していてる求人でも、転職サイトからではなく直接その会社の人事へ電話し、交渉することは可能だと、とある会社の人事部長の方は仰ってました。
この先、子供達に何度も訪れる決断の時。
子供の時から自分で決める機会を作ってあげる。
小さな失敗をたくさん経験させる。
その繰り返しから得られるものは貴重です。
そして大人になった時、その経験から自分の決断に自信を持ち責任を取る覚悟も備わるんじゃないのかなと思います。
子供の人生はお父さんお母さんのものではありません、子供自身の本心を見抜き、たとえそれが自分達の希望するものでなくても、子供自身が後悔しない選択ができるようにしてあげられること。
それは選択肢を広げてあげるための情報収集、準備しましょう。
 子育て親育てブログ
子育て親育てブログ 

